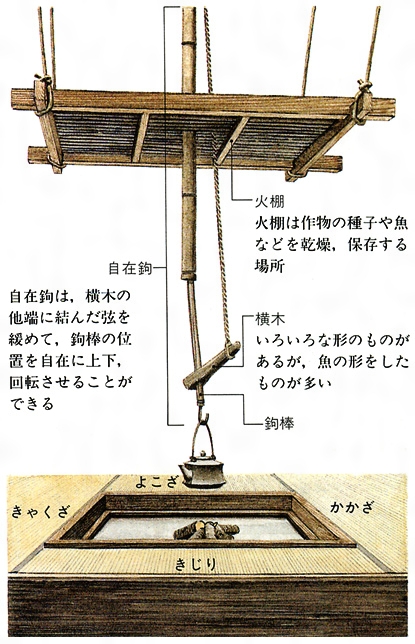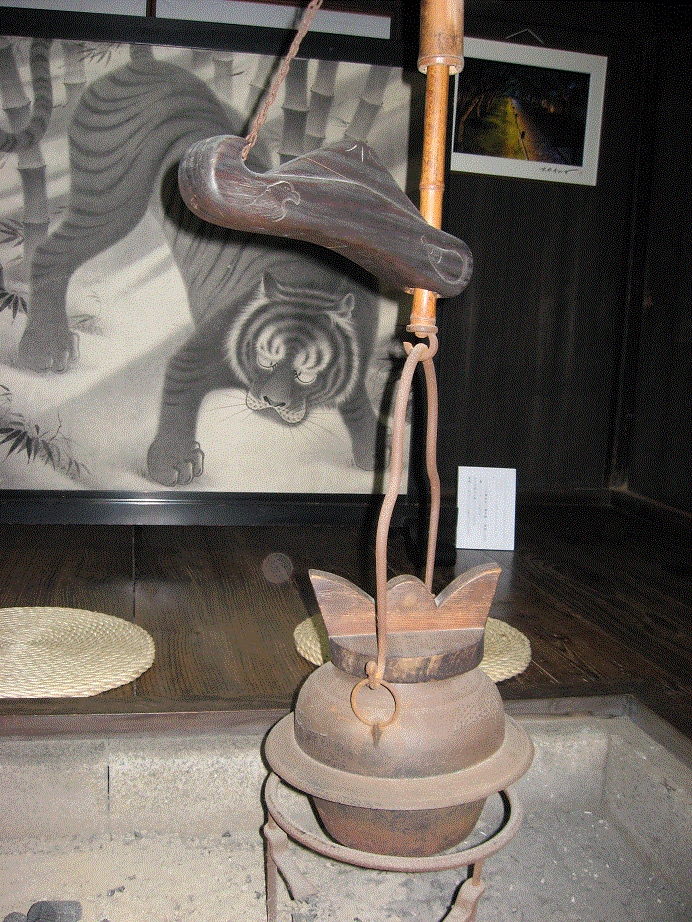山の中に棲んでいる女の妖怪。たいていはおばあさんで、山母、山姫などともいうそうです。実在すると伝えられていて、昔話にも登場します。
背がとても高かったり口が耳まで裂けていたりと、おそろしい風貌です。ときには頭のてっぺんにも口があります。
山姥は、人間を害する恐ろしい存在であるだけでなく、人間に恩恵を与える神さまであることもあり、善悪二面性を持っています。
昔話で例を挙げると、前者は「三枚のお札」「食わず女房」「馬方山姥」など、後者は「糠福米福」「姥皮」などがあります。詳しく見ていきましょう。
「三枚のお札」
小僧(子ども)が山の中に入っていくと山姥に遭遇します。山姥の家に泊まって、便所の神さまの助けなどで逃げだします。逃げながら和尚さまからもらったお札(や鏡やくしなど)を後ろに投げると、山や川や火になって山婆の行く手をさえぎり、小僧は無事寺に帰りつきます。山姥は追跡中に命を落とすか、または和尚さんの知恵でやっつけられます。
この山姥は、ものすごいスピードと迫力で追いかけてきます。足が速いのです。
逃竄譚(とうざんたん)の代表的なものですね。
そして、これは子どもを食べる山姥です。
「食わず女房」
男が、飯を食わない女房が欲しいと言っていると、ある日そんな女がやって来て妻になります。ところが米がどんどんなくなっていくので、男が天井からこっそり見ていると、女は頭の口から握り飯を放りこんでは食べます。男が知らぬふりをして別れてくれと言うと、女は男を桶に入れて山へ連れ去ろうとします。男は逃げて難を逃れます。
菖蒲やヨモギの原にかくれる五月の節句の由来譚と、女が蜘蛛になって夜に男の家にやって来て退治されるという「夜蜘蛛は親に似ても殺せ」ということわざの由来になっている型とがあります。
どちらにしてもこの山姥はものすごい大食漢です。
また節句の由来型は「三枚のお札」と同じく足が速い。俊足です。
後者の山姥は、正体が蜘蛛です。
「馬方山姥」
ここでは馬方(または牛方)の積み荷の魚をつぎつぎと強奪する山姥です。ものすごい大食漢で、しかもすごいスピードで追いかけてきます。これも逃竄譚です。馬方が木の上に逃げ、池に映った馬方を見た山姥が池に飛びこんで死んで終わるというものもありますが、たいていは、馬方は山姥の家に逃げ込んでしまいます。そして、機転を利かせて山姥の餅や酒を飲んだあげく、山姥を殺してしまいます。山姥の正体が蜘蛛であったりします。
柳田国男の『山の人生』によると、足が速くて大食いという性質は、実在すると信じられていた伝承上の山姥の性質でもあったようです。
では、善い山姥を見てみましょう。
「糠福米福」
「米福粟福」ともいいます。継子譚です。ATU510、いわゆるシンデレラ話で世界中に分布します。話の冒頭で姉妹がクリ拾いにいきますが、姉(継子)のふくろにはあなが開いていてなかなかクリがたまりません。新しい袋をくれるのが亡くなった生母なのですが、これが山姥だったりします。芝居見物の時に姉に美しい着物をくれるのも生母(または山姥)です。つまりこの山姥は主人公を助ける神のような存在です。
「姥皮」
これもATU510、シンデレラ話のもうひとつの型です。前半は「蛇婿」の話で、困っている父親を助けて末娘が蛇の嫁になります。娘はうまく蛇をやっつけて逃げだしますが、かくまってくれるのが山姥です。じつは父親が助けてやった蛙の化身だったりします。山姥は娘に姥皮をくれて、娘はそれを着て火焚きばあさんになって雇われます。たまたま娘が姥皮を脱いでいるところを長者の息子に見染められ、結婚して幸せになります。
ほかにも「ちょうふく山の山姥」「山姥の仲人」など、幸せを運んできてくれる山姥がいます。
ところで、民俗学では、山の神の民間信仰が説かれます。
農業者にとって山の神は、春になると山から下りてきて田の神となり、秋には山へ帰って山の神となると信じられてきました。
猟師やきこりなど山で働く人にとっては、山の神は怒らせると恐ろしい、山を支配する神であったようです。神ですから、どちらもお祭りをします。
その山の神の零落したのが山姥だという説が有力だそうです。
そういえば、河童は川の神の零落した姿ですね。
どちらも自然の脅威と自然の与える恵みの両方の側面があり、それが山姥の二面性として表れているのでしょうか。
語りの森では、『語りの森昔話集1おんちょろちょろ』に「めしを食わないよめさん」と「へびの婿さん」を掲載しています。ぜひ読んでみてください。
「三枚のお札」は『語りの森昔話集2ねむりねっこ』に掲載しています。