山と山が背比べをした話が、日本各地に残っています。
これは、その土地に根付いた話で、ほんとうにあったこととして伝えられてきました。だから、昔話ではなく、伝説です。
柳田国男の『日本の伝説』に、「山の背くらべ」として、具体例と解説があります。おもしろいので、ご紹介します。日本地図に落としてみたので、参考にしてください。
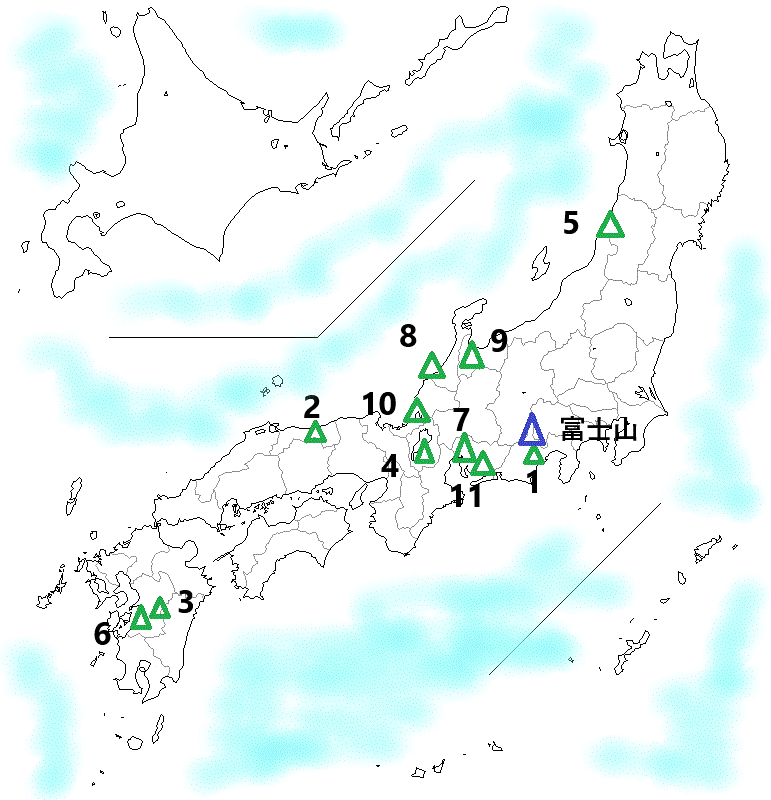
1、愛鷹山(あしたかやま)と富士山・・・静岡県
むかし、諸越(もろこし)の愛鷹山が、富士山と背比べするために、海を渡ってやって来ました。それを見た、足柄山(あしがらやま)の明神さまが、生意気なやつだといって、愛鷹山をけとばしました。それで、愛鷹山の頭がくずれて、かけらが海にちらばってしまいました。そのかけらを集めて作ったのが、浮島が原だそうです。ほら、富士山の東側の小さな山、あれが愛鷹山です。浮島が原には、自然公園があります。
2、孝霊山(こうれいざん)と大山(だいせん)・・・鳥取県
むかし、韓(から)の国から、大山と背比べするために高い山がやって来ました。韓から来たので韓山といいます。韓山は、大山より少しばかり高かったので、大山は腹を立てました。大山は、木履(ぼくり:木をくりぬいて作ったくつ)をはいたまま韓山の頭をけ飛ばしました。それで、今でも、韓山の頭は欠けていて、大山よりだいぶ低いのだそうです。韓山は、今は、孝霊山と呼ばれています。
3、根子岳(ねこだけ)と阿蘇山(あそざん)・・・熊本県
阿蘇山の東南に、猫岳という珍しい形の山があります。むかし、猫岳は、いつも阿蘇山と高さくらべをしていました。阿蘇山は、怒って、ばさら竹の杖で、しょっちゅう猫岳の頭を打っていました。猫岳は、頭がこわれてでこぼこになってしまいました。猫岳は、今は根子岳と書きます。
4、浅井(あさい)の岡と伊吹山(いぶきやま)・・・滋賀県
むかし、伊吹山の神さま多々美彦(たたみひこ)の姪である浅井の岡の浅井姫は、おじさんの伊吹山と高さくらべをしました。そして、ひと晩のうちにするすると伸びて、伊吹山より高くなりました。多々美彦はたいへん腹を立て、剣を抜いて浅井姫の首を切りました。首は琵琶湖に飛んで行って島になりました。これが竹生(ちくぶ)島です。
5、鳥海山(ちょうかいさん)と富士山・・・山形県
むかし、鳥海山は、われこそは日本で一番高い山だと思っていました。そころがある日、旅人がやって来て、富士山のほうが高いといいました。鳥海山はくやしくて、腹を立て、いてもたってもいられず、頭だけ遠く海に向かって飛んで行ってしまいました。それが、今の飛島(とびしま)です。
6、飯田山(いいださん)と金峰山(きんぽうざん)・・・熊本県
むかし、飯田山と金峰山が高さくらべをしました。いつまで争ってみても勝負がつきません。そこで、両方の山のてっぺんに樋(とい)をかけ渡して水を流してみようということになりました。すると、水は、飯田山の方に流れて、飯田山の方が低いということになりました。そこで、もう今からはそんなことは「言いださん」といったので、飯田山と呼ばれるようになったということです。飯田山のてっぺんには、その時の水がたまった池が今でもあるそうです。
7、尾張富士と本宮山(ほんぐうさん)・・・愛知県
むかし、尾張富士と本宮山が背比べをしました。山のてっぺんに樋をかけて水を流すと、尾張富士のほうに流れました。尾張富士が負けたので、ふもとの村の人たちは、年に一度のお祭りに、石を引いて行くようになりました。少しでも山が高くなるようにとの願いからです。今は石上げ祭りといって、8月の第1日曜に行われているそうです。
8、白山(はくさん)と富士山・・・石川県
むかし、白山と富士山が背比べをしました。山のてっぺんに樋をかけて流すと、白山に向けて水が流れ始めました。それを見ていた白山のふもとの人たちが、急いで、はいていたわらじをぬいで樋のはしに当てがいました。すると、ちょうど同じ高さになりました。それで、今でも、白山にお参りする人は、かならずわらじの片方をぬいで、置いて帰るそうです。
9、立山(たてやま)と白山・・・富山県
むかし、立山と白山が背比べをしました。すると、立山のほうが、わらじ一足分だけ低かったので、立山は、たいへん悔しがりました。そこで、立山に参詣する人たちは、わらじを持って登るとご利益があるといわれています。
10、飯降山(いぶりやま)と荒島山(あらしまやま)・・・福井県
むかし、飯降山が荒島山と背比べをしました。すると、飯降山のほうが馬のくつ一足分だけ低かったそうです。そこで、飯降山に石を持って登ると、願い事がひとつだけかなうといわれるようになりました。
11、本宮山と石巻山(いしまきやま)・・・愛知県
本宮山と石巻山は、大昔から背比べを続けていますが、まったく高さに差がありません。それで、いまでも、石を手に持って登れば少しもくたびれないけれど、小石ひとつでも持って帰ると、罰が当たるといわれています。
これらの伝説は、柳田国男が、古い文献から探しだしたものです。けれども、日本各地を歩けば、もっとたくさんの山の背くらべが残っていると思います。
山が擬人化されているというより、山には神さまがいて、その神さまはとっても人間的だったのだと感じます。古い土着の信仰から生まれた伝説なのでしょう。
どれもコミカルな話で、山に親しみがわいてきます。
「全国山の背くらべツアー」なんてあれば、行ってみたいです。そして、山をながめながら、山たちの表情を想像して楽しみたいです。
ところで、これは、日本だけの伝説で、世界的にもにあるのでしょうか?知りたいです。
この記事を書いた後で、八ヶ岳と富士山の背比べの文献を見つけました。語れる形に再話したので、ごらんください。こちら→