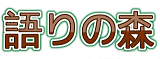うんちく池
昔話の語法
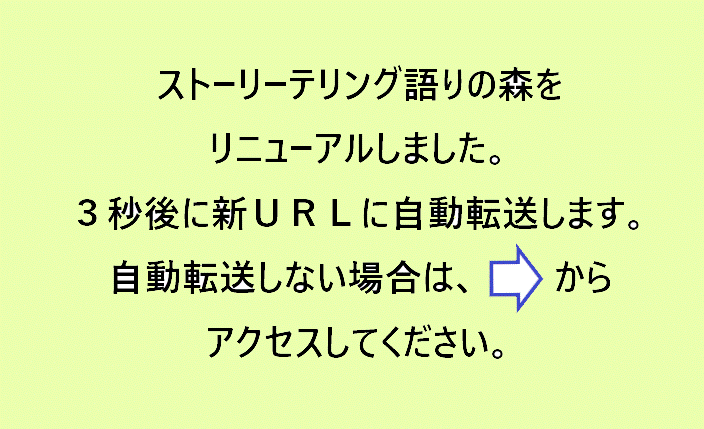
 平面性
平面性
昔話では、日常の世界 ( 此岸 ) とあちらの世界 ( 彼岸 ) との間に断絶が感じられません。そして、地理的に遠くにあると表現することで、精神的に離れていることを表します。これは昔話の一次元性として説明しましたが、また、此岸と彼岸が同じひとつの平面に存在するという意味で、「 平面性 」 ということができます。
昔話では、人も物もストーリーも、時間さえも、あらゆるものが徹底的に平面性という原理のもとで描かれます。あらゆるものに奥行きがないのです。
![]() 奥行きがない、つまり立体的でないってこと? それって、どういうこと???
奥行きがない、つまり立体的でないってこと? それって、どういうこと???
まず、昔話に登場する 「 物 」 を見てみましょう。
杖、指輪、鍵、刀、針、動物の毛、鳥の羽、しゃもじ、うちわ、などなど。平べったい線状のものが好んで使われます。そして、それらのものは、日常的に人に使われることはありません。使い古された履歴を持っていません。だれかの手あかがついているわけではないし、だれも愛着を持っていません。そういう意味で立体的でないのです。
物はふだんは使われず、ストーリーに必要な時だけ、一回限り使われて退場します。
![]() なるほど。「尻鳴りしゃもじ」の話に出てくるしゃもじがそうだね。あのしゃもじ、ふだんご飯をよそうときに使わないで、お尻を鳴らしたり止めたりするときにしか使わないもんな。特殊な場面でだけ使われている。
なるほど。「尻鳴りしゃもじ」の話に出てくるしゃもじがそうだね。あのしゃもじ、ふだんご飯をよそうときに使わないで、お尻を鳴らしたり止めたりするときにしか使わないもんな。特殊な場面でだけ使われている。
そうですね。「鼻高扇」の鼻を伸びちぢみさせる扇、「天狗の隠れ蓑」の姿を消せる蓑、「宝下駄」の、はいてころべば小判の出る下駄。などなど、いくらでも見つけられます。
では次に人物の描かれかたを見てみましょう。こちらのほうがわかりやすいかもしれませんね。
 図形的に語る
図形的に語る
物が立体的に描かれないのと同じように、人物や動物も肉体的な奥行きがありません。
リュティ先生いわく。
「 われわれはその肉体の奥行きや立体性を見ているのではなくて、ただ表面だけを見ている。 」
たとえば、「手なし娘」が手を切られる場面では、表面的に手がなくなるだけで、血も流れないし激痛で転げまわるわけでもありません。父親に手を切られるという仕打ちに、精神的な苦しみを訴えることもありません。馬方は馬の脚を切って投げますが、馬はそのまま走りつづけます。昔話ではそのようなシーンに枚挙のいとまがありません。
具体例→
これは、人物や動物が、まるで切り紙細工のように図形として表現されているのです。もちろん、聞き手が頭の中で切り紙細工を見ているというのではありません。聞き手は、ストーリーに必要な程度にちゃんとイメージして聞きます。でも、もし立体的に肉体的に描写されていたらどうでしょう。聞き手はそちらに気を取られ、ストーリーに集中できませんね。
リュティ先生いわく。
「 昔話の登場者はあたかも紙で作った図形のようで、好きなように切りとってもべつに本質的変化が生じるものではない。原則的にいって、このような傷害を受けても肉体的、精神的苦痛は表明されない。 」
![]() こういう切ったりする場面があるから、昔話は残酷だっていう人がいるんだね。けど、けっして残虐には描写しないんだ。もしこれがテレビなんかの実写だったら見ていられないだろうけどね。図形的に語っている限り残酷には感じられないんだね。とくに子どもはそうだよ。ストーリーのなり行きに集中しているからね。
こういう切ったりする場面があるから、昔話は残酷だっていう人がいるんだね。けど、けっして残虐には描写しないんだ。もしこれがテレビなんかの実写だったら見ていられないだろうけどね。図形的に語っている限り残酷には感じられないんだね。とくに子どもはそうだよ。ストーリーのなり行きに集中しているからね。
登場人物が涙を流す場面があります。それは、悲しみや悔しさや喜びを表すためではなく、話のすじに必要だから涙が流れるのです。血もそうです。傷の深さ痛さを表すために血が流れるのではありません。涙も血も特定の役割があって流れるのです。
具体例→
![]() 図形的に語る。つまり肉体的奥行きがない語りかたをするということだね。それが昔話の特徴「平面性」があらわれているってことなんだ。なるほど~。
図形的に語る。つまり肉体的奥行きがない語りかたをするということだね。それが昔話の特徴「平面性」があらわれているってことなんだ。なるほど~。
 外的刺激
外的刺激
昔話では物も人物も奥行きを持ちません。肉体的な奥行きだけでなく、精神的な奥行きもないのです。
現実の世界では、ひとりの人間の中に相反する性格が複雑にからみあっていて、その葛藤があるものですが、昔話では、それがない。いいお爺さんは、ぜったいにいいお爺さん、悪いお爺さんは、ぜったいに悪い。これは、正直な性格といじわるな性格をふたりの人間に分け与えているのです。
「舌切り雀」のおじいさんとおばあさん、「瘤取り爺」「花咲爺」「にぎりめしころころ」のふたりのお爺さん、「ホレばあさん」のふたりの娘。「灰かぶり」の主人公とふたりの姉。具体例はいくらでも思いつきますね。
そして、そのような性格は、言葉で説明するのではなくて行動で示されます。というのは、精神的なことも、ストーリーの上に行動として平面的に並べられるのです。
具体例→
そして、悩むこともない。人物は、考えこんだり悩んだりせずに行動します。つまり、内面がストーリー上の行動であらわされているのです。
具体例→
リュティ先生いわく。
「感情や性質はあるひとつの平面に投影され、その同一平面にほかのすべてのものも投影されている」
![]() 善人と悪人にバチッと区別があるんだね。だから、わかりやすいんだ。
善人と悪人にバチッと区別があるんだね。だから、わかりやすいんだ。
それに、ストーリーや場面がきちっとイメージできれば、登場人物の心の中はいちいち言葉で説明しなくてもいいんだ。だって、聞き手は自分自身が登場人物になって、考えたり心を動かしたりするからね。
あ、そうか、ストーリーは語り手に、心は聞き手にあるんだ!
ところで、「外的刺激」って、なんのこと?
昔話の登場人物には精神的な奥行き(=内面)がないので、前へ進むには外からの刺激、つまり外的刺激が必要です。「外的原動力」といってもいいでしょう。
たとえば、贈り物、課題、忠告、禁令、困難、幸運なチャンス、などなど。
具体例→
そして、精神的な成長を物語ろうとしても、主人公は内面を持ちません。そこで、人物の性格が行動で示されたのと同じように、心の成長は旅というストーリーであらわされるのです。
リュティ先生いわく。
「昔話の主人公は本質的なものと出会うためには旅に出なければならない」
![]() この旅は、まっすく前に向かって進んでいく旅だ。
この旅は、まっすく前に向かって進んでいく旅だ。
いい言葉だなあ。人生だって旅だもの。
 周囲の世界
周囲の世界
昔話では、登場人物について、どんな町で育ったかとか、どんな家柄なのかとか、周囲の環境は説明されません。人物が立体的に描かれることがないのです。周囲の世界は、ストーリーに必要な場合のみ最低限描写されるだけです。
「むかしあるところに、男とおかみさんがおりましたが、子どもがあんまりたくさんいてみんなに食べさせることができなかったので、下の三人の女の子を森に捨てました。三人はどんどんどんどん歩いていきましたが…」
これは、「かしこいモリー」の冒頭です。男とおかみさんがどこで暮らしていたのか、何歳なのか、ふたりのなれそめもわかりません。それどころか名前もありません。わかっているのは子どもがたくさんいることと、極端に貧しいことだけです。そして、昔話にとってはそれで十分なのです。そこからストーリーが始まるからです。
経歴不明の両親に捨てられた女の子たちの年齢も性格も描かれません。名前もわからないし、捨てられたからどんどん歩いていくだけです。泣きわめいたりもしないし、親に捨てられた子どもの内面はいっさい語られません。ほんとうなら、三人の性格によって違った反応があるはずですが、それもなし。
また、「白雪姫」の女王は、女王としての仕事やおつき合いがあったろうに、それらは語られません。彼女がやったことは、鏡を見ることと白雪姫を殺すことだけです。ストーリーに必要なことしか描かれていないのです。
小説ならば、女王はどのような家柄の娘だったのか、どのような経緯で王と結婚したのか、王は彼女を愛したのか、夫婦の間はうまくいっていたのか、魔法の鏡をどこから手に入れたのか、彼女の家に代々伝わっていたのか、他国との関係はどのようで、女王は外交にどのような力を発揮していたのか等々を描写して、なぜ白雪姫を殺そうと考えるに至ったかを心理的に追及するでしょう。
昔話はそれらの描写をいっさい放棄しています。
このことを、「白雪姫」の女王は「女王として本来持っているべき環境を捨てている」といいます。
「かしこいモリー」の王さまは、モリーに大男から盗ませることしかしていません。王としての環境を捨てているのです。「絵姿女房」のお殿様しかり。
リュティ先生いわく
「昔話の人物は内的世界をもっていないばかりでなく、周囲の世界も持っていない」
そして、主人公は、出会った人物とその時その時に関係を持つのみで、ストーリーが進めば別れていきます。ストーリーとは別に末永くおつき合いすることはないのです。主人公は両親からも離れていきます。
「天までとどいた木」では、主人公ヘルムが木を登っていく途中で、月曜日のおばあさんから土曜日のおばあさんまでつぎつぎに出会って、泊めてもらいますね。でも、そののちもおつき合いをするなんてことはありません。それぞれ一回こっきりの関係です。具体例→
「三本の金髪のある悪魔」のわき役たちを考えてみてください。一軒家に住むおばあさん、盗賊たち、門番、渡し守。みなストーリー上での自分の役割を終えたら舞台裏に消えてしまいます。
リュティ先生いわく
「昔話の登場人物相互のあいだは、固定した永続的関係は存在しない」
昔話のストーリーにとって重要な役割を果たす「彼岸からの援助者」との関係も同じです。まず、内面的なかかわりは持ちません。援助者は、主人公の精神的な支えになるのではなく、実質的な役に立つ贈り物をあたえます。主人公と援助者との関係は、贈り物によって具体化されるのです。精神的な関係ではなく、目に見える関係として示されるのです。
「七羽のカラス」のあけの明星は、ひな鳥の骨を贈り物としてくれます。兄たちをすくうための鍵です。
「仙人の教え」の仙人は、課題の解決方法を教えてくれます。言葉による贈り物です。
「金のがちょう」のこびとは、なんでもくっつくがちょうをくれます。おかげで主人公はお姫さまを笑わせることができます。さらに、主人公に代わって、王さまの難題を解決してくれます。
![]() 他人との関係は、目に見える関係として語られるんだね。そうすればイメージできるし、わかりやすいんとだ。
他人との関係は、目に見える関係として語られるんだね。そうすればイメージできるし、わかりやすいんとだ。
どんなにありがたくってうれしいかってことを、いくら懇切丁寧に説明されたって、「ふ~ん」って思うだけで実感わかないもの。
でも、「ガラスの山を開ける鍵をもらった」って聞いたら、「やった~」って思うし、「鍵を失くした」って聞いたら、「ええ~っ」って思うものね。
彼岸者は、ちょうど必要なときに、ちょうど必要な贈り物をくれます。そして、役割が終わったら即退場します。
主人公は贈り物を決定的に重要なときに使うだけです。
「尻鳴りべら」のしゃもじは、お尻を鳴らすか止めるかするときだけ使います。ふだんご飯をよそうときに使いません。ストーリーに必要なときにピタッと役割を果たしで退場するのです。
![]() とことんストーリー中心だね。そして、そのストーリーの一本道を最初から最後まで歩くのは主人公だけ。つまり、昔話はとことん主人公中心の物語なんだ。
とことんストーリー中心だね。そして、そのストーリーの一本道を最初から最後まで歩くのは主人公だけ。つまり、昔話はとことん主人公中心の物語なんだ。
 無時間性
無時間性
昔話の登場人物には、肉体的にも精神的にも奥行きがありません。立体的な人間として描いていないのです。周囲の環境も語らないし、その人の履歴も語りません。先祖や子孫との関係も語られません。そもそも「時間」との関係がないのです。
たとえば、「いばら姫」(グリム童話)で、主人公はつむに指をさされたとたん、百年の眠りに落ちます。そして、百年目に王子がキスをしたとたん、目をさまします。目をさましたとき、姫は何歳ですか? そうです、15歳です。百年の年月は、主人公の外見に何の変化も与えていません。服装などの風俗も社会もすべて百年前のままであり同時に百年後の今なのです。ふたりは下におりると結婚式をあげます。まるで百年の眠りなどなかったかのように、ごく当たり前に。
![]() リアルに考えたら、お姫さまは115歳だし、115歳のお姫さまと王子が結婚するなんてこと、考えられないよね。時間的奥行きを持たないおひめさまと、時間的奥行きを持たない王子さまが、同じ平面上にいるんだ。
リアルに考えたら、お姫さまは115歳だし、115歳のお姫さまと王子が結婚するなんてこと、考えられないよね。時間的奥行きを持たないおひめさまと、時間的奥行きを持たない王子さまが、同じ平面上にいるんだ。
ところが同じ場面を写実的な小説で描写すればどうなるでしょう。ペローの「眠りの森の美女」と読み比べてみてください。具体例→
リュティ先生いわく
「平面的な昔話の世界には時間の次元も欠けている。たしかに昔話のなかには若者もいれば老人もいる。(略)ところがしだいに年をとっていく人間は昔話には存在しない」
これを昔話の無時間性といいます。
時間が「省略されている」のではありません。時間という次元が「ない」のです。
魔法で眠らされていたあとでも、おおかみのお腹にのみこまれていたあとでも、主人公は苦境時代の痕跡を全く残していません。「かえるの王さま」(グリム童話)では、蛙はいきなり美しい王子に変身し、蛙的なものは何も残っていません。そしてお姫さまは、さっきまで蛙だった男とよろこんで結婚します。
時間的な奥行きがなく、眠る―目覚める、といった「ことがら」が時間を無視して同一平面上に並べられるのです。蛙になる―王子になる、呪いにかかる―呪いがとける、等々・・・。
そして、昔話における魔法は、けっして先祖から子孫にまで影響を及ぼすことはありません。いばら姫にかけられた呪いは、とかれるとそれでおしまい。子孫に影響はありません。蛙だった王子の子孫にときどき蛙があらわれるなんてこともありません。伝説ならば、いばら姫のつむが呪いのつむとして、子々孫々秘密の部屋に厳重にしまっておかれるかもしれませんね。
さて、時間の経過がないので、あらゆる変化は一瞬にして起きます。徐々に育ったリ、少しずつ衰えたりしないのです。とても機械的です。具体例で説明しましょう →こちら
昔話は、このように時間を語らないことによって、ストーリーを先へ先へと進めていきます。ストーリーの行き着く先は満足な結末、つまり主人公の幸せです。それは、主人公である聞き手の求める結末でもあるのです。
![]() 子どもは主人公が幸せになることだけに心を集中させて聴いているものね。語り手はそれに応えるべく語っているんだ。それに、一瞬にして生きかえったり目が見えたりすると、とってもわくわくするよ。
子どもは主人公が幸せになることだけに心を集中させて聴いているものね。語り手はそれに応えるべく語っているんだ。それに、一瞬にして生きかえったり目が見えたりすると、とってもわくわくするよ。